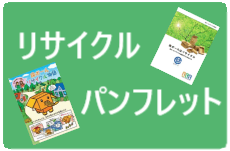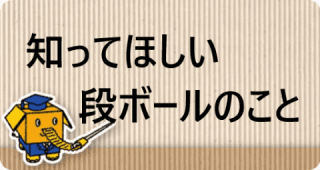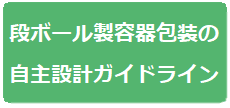リサイクル可能な全ての段ボールへの表示方法
〔1〕リサイクルマークの基本デザイン
段ボールのリサイクルマークは、「国際リサイクル・シンボル」と「ダンボール」の文字で構成され、表示スペースや段ボールの大きさ等に対応して相似形で運用する。
□一般的な表示

「段ボールの国際リサイクル・シンボル」
・その段ボールがリサイクル可能であることを示す、世界共通のシンボルである。
「ダンボール」の表記
・その段ボールがリサイクル可能であることを示す、世界共通のシンボルである。
「ダンボール」の表記
□「段ボール」の表記
| ■ | 書体は太ゴシック体、又はそれに準じる視認性の良い字体を使用する。 |
|
■
|
一般に使用されている段ボールではなく「ダンボール」を使用するのは、字画の少ないダンの方が段ボールへの直接印刷で鮮明になりやすいこと、及び子供でも分かりやすいと思われることによる。 |
|
■
|
配置は変更可能である。
印刷デザイン上の制約、あるいは他の容器包装の一括表示により使用部位の表記を行う場合などには、ダンボールの文字を下図のように配置してもよい。
|
文字配置例
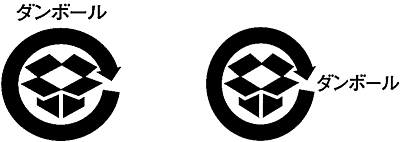
□「ダンボールはリサイクル」の表記
輸送用の外装箱など、印刷スペースに余裕がある場合には、"その段ボールを積極的にリサイクルすべき" とのメッセージとして、「ダンボールはリサイクル」と表記することができる。

〔2〕リサイクルマークの表示サイズ
段ボールのリサイクルマークは、印刷方法により再現性に差が生じるため、印刷方法による最小サイズを下記の通りとする。
□段ボールへ直接印刷<※1>を行う場合
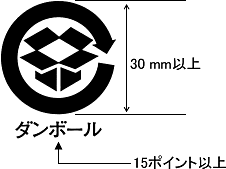
<※1>フレキソインキ又は速乾性インキにより、段ボールに直接印刷を行う方法。
□プレプリント<※2>の場合
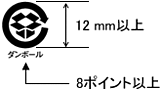
<※2>段ボールに貼合する前のライナにあらかじめ印刷してから、中しん原紙と貼り合わせる方法。
□枚葉貼合<※3>の場合
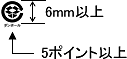
<※3>紙器用板紙にオフセット印刷などを施して、片面段ボールに貼り合わせる方法。
■ 留意事項
|
■
|
視認性を容易にするためには、リサイクルマークは大きい方が望ましい。 |
|
■
|
特に、段ボールに直接印刷を行う場合には、段ボールの構造と印刷方法の技術的な制約に注意する必要がある。
リサイクルマークの大きさが30mm以下になると、白ヌキ部分のつぶれが生じる恐れがあるため、印刷機の運転速度低下、印版の洗浄、検品などにより生産性が阻害される。
|
|
■
|
リサイクルマークを反転して印刷する場合には、容易に判別できる大きさの確保に留意することが必要である。
|
〔3〕リサイクルマークを表示する色
リサイクルマークは、ブランドやデザインを印刷するために用いる色のうち、視認性の良い方の色を用いることが望ましい。
■ 留意事項
|
■
|
ブランドやデザインを印刷する色以外の色を用いる場合には、印刷色数が増加し、自社が保有する印刷機の色数を超える場合には印刷が2工程になる。 |
〔4〕リサイクルマークの表示場所
リサイクルマークの表示場所は、最終排出者が視認し易いことを原則に、事業者間で自由に決めることができる。
■ 留意事項
|
■
|
リサイクルマークは、流通段階でも視認できる長さ面、幅面、天面に表示することが望ましいが、印刷デザインなどによる制約がある場合には、折りたたんで排出するときに視認できる底面に表示してもよい。 |
〔5〕無地の段ボールへの対応
無地の段ボールについては、リサイクルマークの直接の表示を省略することができる。
■ 留意事項
|
■
|
無地の段ボールとは、その製造段階で印刷が可能な工程を経ないものである。
・単一色による全面印刷(いわゆる色無地の印刷)や色ライナを使用して印刷工程を経ない段ボールは、無地の段ボールに含まれる。
|
| ■ | スタンプは印刷に含まれる。 |
|
■
|
刻印・エンボス等によりリサイクルマークを施すことは、段ボールの構造(厚さ、復元力等)から好ましくない。実際に、消費者から判別できないという意見が寄せられている。 |
|
■
|
無地の段ボールであっても実施可能な範囲での対応を図ることが望ましいが、プラスチック製のシールやラベルでリサイクルマークを施すことは、異物の混入となるので段ボールのリサイクルには好ましくない。 |
〔6〕輸出する物品を梱包する段ボールへの対応
輸出する物品を梱包する段ボールへの表示については、相手国(あるいは地域)の輸入業者の指示に従う。
■ 留意事項
|
■
|
特に、西欧諸国では、1990年代初期に各国で法律に関連するリサイクル・シンボルが定め られており、それらが最優先される場合がある。 |
〔7〕輸入する物品を梱包する段ボールへの対応
物品を輸入・販売する事業者が、物品を梱包する段ボールの素材、構造、デザイン、印刷などの仕様に関して指示できる場合には、このガイドラインに準じてリサイクルマークの表示を行なう。
■ 留意事項
| ■ | 事業者が上記の仕様などを指示できない場合には、[5]無地の段ボールへの対応 に準じる。 |
〔8〕リサイクルが困難な段ボールへの対応
段ボールを製造あるいは利用する段階で製紙原料として利用困難な素材が複合され、それらの素材が分離不可能な段ボールには、リサイクルマークを表示できない。
■ 留意事項
|
■
|
段ボールの「国際リサイクル・シンボル」は、「その段ボールがリサイクル可能(製紙原料として利用可能)である」ことを示す世界共通のシンボルである。段ボール及び段ボール古紙は国際的に流通しているので、製紙原料として利用困難な段ボールに「国際リサイクル・シンボル」を表示することは、相手国のリサイクル機構を混乱させる恐れがある。
|
|
■
|
段ボールのリサイクルは、最新の製紙技術に基づいて判断しなければならないため、製紙原料として利用困難な段ボールについては、下記の方法で確認されたい。 ・自社が購入している段ボール原紙メーカーに確認する。 ・段ボールリサイクル協議会に確認する。TEL: 03 (3248) 4853 ・財団法人古紙再生促進センターのホームページより、古紙の取引における品質基準「古紙標準品質規格」を参照する。>>財団法人古紙再生促進センターのホームページ http://www.prpc.or.jp |
|
■
|
今日、製紙原料として利用困難とされている段ボールには、下記のようなものがある。
・ろう (蝋)段(ワックス付段ボール)、アルミ箔をラミネートしたもの ・プラスチック製緩衝材や布などを貼り合わせたもの
・魚・洗剤類・線香・香辛料などの臭いのついた段ボールケース |